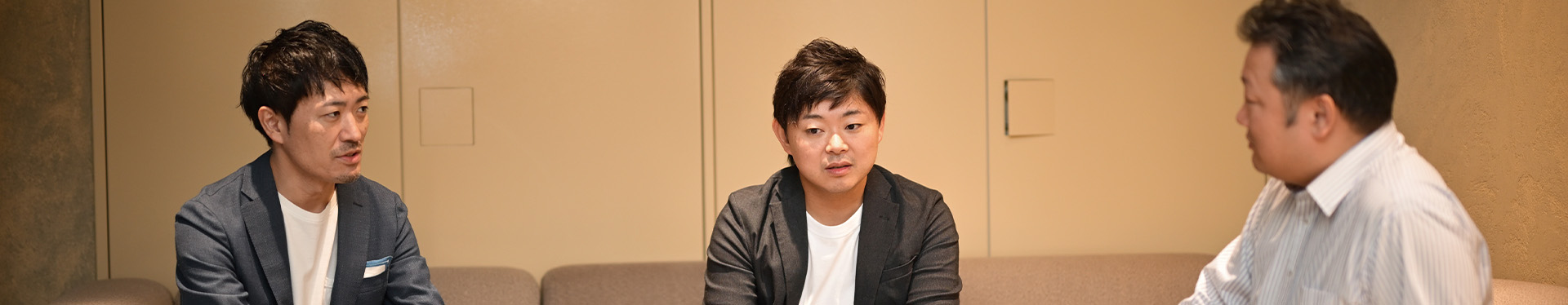医療DXと医療広告の未来
医療業界の課題について、医療DX×医療広告が解決すべきこと、そしてこれからどのようにすべきかなど話し合ってもらいました。
対談メンバー

2023年入社
経営推進本部 SC事業企画部
部長
原拓也
医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、スマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。

2017年入社
カスタマーサポート本部
本部長
中野大輔
WEB制作会社にてWEBディレクターおよび制作・カスタマーサポート・提案営業・広告出稿および審査・各種サイト運用など、幅広い業務を経験し、ヒーローイノベーションに入社。

2014年入社
経営推進本部 営業企画部
部長
原田圭輔
クリニック開業から、集患支援、運営オペレーション改善まで幅広く担い、カスタマーサクセス事業の責任者兼営業統括として、医療機関の成長戦略立案からその実現までを包括的にサポート。
医療業界の課題と私たちの挑戦
医療業界の課題と私たちの取り組みについて話し合いたいと思います。まず、業界の現状と課題をどのように考えていますか?


最近特に気になっているのは、医療の一極集中と医療過疎化の問題ですね。医師の働き方改革の影響で、独立(開業)を志す医師が都市部に集中する傾向がありますよね。その結果、高齢者の人口割合が多い地方に対して、医師・医療機関が不足する医療格差が広がってることが課題ですね。

これには矛盾があって、クリニックは患者が来ないと経営が成り立たないので当然人口の多い都市部で開業したい、一方で過疎化の進む地方は医師不足。本来医療を受ける・受けたい生活者は地方に多いのに、専門医も広報発信力も都市部に集中してしまってますよね。

現場の感覚としても、最近は「反響をどう増やすか」という相談が増えてきていて、競争が激化している市場です。クリニック同士の競合が多い中で、効率化や差別化の方法を求める医師が増えてますね。

都市部に集中しすぎですよね。当社のような企業が、全てを解決できるわけではないですけど、地方の開業数を増やすということが現実的に難しいのであれば、医療提供のオンライン化やデジタル化は必須の手段となります。

地方にも、地域医療に貢献したいと強い使命感を持たれた専門医もいらっしゃいますし、その先生に通いたくて遠方から来院される患者さんもいて、効果的な広報活動がができないことが理由で閉院を余儀なくされるクリニックもあると考えます。医師自体の高齢者も課題ですね。

前提、医師も全体的に高齢化が進み、地方で広い診療圏を診ている先生は、インターネットやIT・DXツールにあまり興味を持たれない方も多いと感じます…患者さんもご高齢ですし。それでも、地域特性に合わせた効果的な広報活動を実施すれば無駄な労力も減らせると思うんですよね。

それと、医療費の問題も大きいですね。国全体で40数兆円の医療費が嵩む中、人口減少社会でどう持続可能にしていくかが課題ですよね。DXによって医療費全体の最適化に貢献することで、結果的に国の負担を軽減することも重要だと思います。

医療費の問題と人手不足はセットで考えないといけないですよ。医療費の内訳は薬剤、診察、入院・手術、材料、そして人件費。「人が足りない」と言っているのに、医療需要ばかりが増加してしまってる現状ですから。

本当にそうですね。医療DXの最終的な目標は、タスクシフトだと思います。会計や問診などを出来る限り機械化して、医師や看護師をはじめとする医療従事者が本来の医療行為や患者対応に集中できるようにすることが理想ですね。
医療広告・医療DXの特徴と使命
医療広告や医療DXの他業種との違いについて教えてください。医療ならではの特徴はありますか?


医療広告に関して、最大の特徴は医療広告ガイドラインの存在ですね。情報を扱う上でこのガイドラインをしっかり守らないと厚生労働省から指摘が入ります。一般の広告と違って、規制が厳しいんです。

法規制の厳しさは社会的意義の大きさを表してますよね。たかが風邪でも、患者さんは自分の命を預けているわけです。法規制の厳しさは、この業界に携わる者としては遵守すべきと同時に、使命感として誇りに感じられるポイントだと思います。

そうですね。医療情報は普段目にする一般的な広告とは重みが違いますね。間接的にですが、人の命に関わる情報を扱っているという責任があるので。

また、国民皆保険制度の下で事業展開するという特徴もあるので、法改正・制度改正も常に注視していないといけないですし。診療報酬の仕組みの理解も必要です。ただ、この制度改正はチャンスでもあって、24年度月の診療報酬改定に併せて「療養計画書作成サービス(メルプドキュメント)」という新サービスを出しましたし、変化に素早く対応しながら医療機関と伴走することが求められてる気がします。

本当にそうですね。診療報酬の点数次第で市場が一気に動きます。オンライン診療も点数や条件が変わればさらに普及するでしょう。国策と医療機関のニーズ双方に併せていくことがビジネスチャンスに繋がりますね。

”クリニックの経営を医療DXが土台となって支える”って一見抽象的な表現ですけど、具体的に言うと、患者さんには最適な医療を提供しながら、クリニックの収益源である診療報酬を適切かつ効率的に得られるための仕組みのお手伝いが医療DXの一つであり、求められることなんじゃないかなと。

24年度の診療報酬改定で減収になるのに業務が増えるのではないかと不安を感じておられた先生も多く、それがきっかけで、メルプドキュメントが生まれましたからね。

ほんと、クリニック経営ってどんどんスリム・スマートになっていってますね。
ヒーローイノベーションの強みと価値観
ヒーローイノベーションの強みや独自性について教えてください。私たちは何を目指しているのでしょうか?


創業当時の話ですが、医療広告業界では、当時の主要な企業は1軒あたり約80〜90万円でサービスを提供していました。私たちは後発でしたが、あえて120〜150万円と高い価格設定をしました。違いは何かというと、ホームページのクオリティです。
価格競争はしたくなかったんです。「他社がこの価格だから、うちはもっと安く」という流れは業界全体にとって良くない。サービスを受ける人たちの目線で考え、本当に価値のあるものを適切な価格で提供した。その結果、競合会社から「ヒーローに市場を奪われている」と良い意味で言われるようになったんです。そういう健全な「価格ではなく提供価値の競争」という意識が業界全体に良い影響を与えると思うんですよね。

そこがヒーローの素晴らしいところですね。沢山の競合がいる中でも「共に業界発展に尽くそう」という姿勢で、業界全体の発展のために他社や競合とでも手を取り合って尽くしていく。そういった横の繋がり・連帯性を重視するマインドセットがヒーロー独特の魅力だと感じています。

パートナー企業との関係構築や営業力は本当に強みです。参入障壁が高いのは、この業界はそもそも1社だけで戦える業界ではなくて、他社と協力しながらでないと絶対うまく行かない。医療は1つのサービスで完結なんてしなくて、複数のサービスが絡み合ってるからこそ、皆が協力して医療をよりよくしている気がしてます。

おー、確かにそうですよね。
あと、HEROはエンジニアやサポートの人たちも活躍できる環境がありますね。営業がしっかり先生たちと関係構築していることで、クリエイターの提案も受け入れてもらいやすくなりますし、より良いものを作れてますね。

他社にも内製の仕組みはあると思いますが、ヒーローは、フロントとして活躍する営業・ディレクターと顧客の信頼関係が素晴らしいと感じます。クリエイターが作ったものに対して、営業が本当に感謝してくれるんです。デザインへのフィードバックが自然な流れで返ってくる環境は素晴らしいと思います。
未来へのビジョン
ヒーローイノベーションが目指すものについて教えてください。


やはり「医療を便利に、わかりやすく」というミッションはそのままです。ホームページだけでなく、アナログ媒体も含めて、様々なエリアや対象者に合わせた広告媒体を活用し、医療をより身近にしていきたい。医療はまだまだわかりにくい部分が多いので、プロモーション事業でわかりやすくしていきたいですし、スマートクリニック事業では医師や医療スタッフ、患者さんにとって便利なサービスを実現していきたいと思います。

私は夢として数値目標も持っています。日本のクリニック約17万軒(医科・歯科)の最低でも半分にヒーローのサービスを届けたい。目指せ半分!って思ってます!どの企業もまだ達成していませんので。そしてクリニックと患者さんに「ヒーローのサービスを使って便利になった?」と聞いたら「まあね」「良かったよ」と言ってもらえること。それは「アナログ媒体の診察券やチラシの印刷が綺麗だった」でも良いし「問診システムやレジを導入して良かった」でも良いので、それを一つ一つ積み重ねていきたいですね。